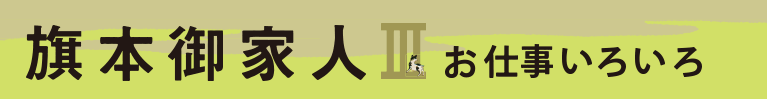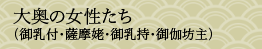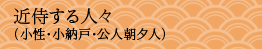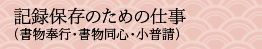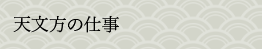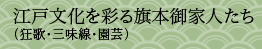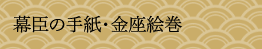[請求番号 166-0185]
御乳持に御家人の妻女(妻と娘)が多かったのは、安楽な生活に慣れた旗本の妻女では御乳持のストレスに堪えられなかったから。しかし子だくさん(男女あわせて50人以上)の家斉の時代には、そうも言っていられません。
寛政4年(1792)7月、家斉の長男の竹千代が誕生したとき(翌5年6月没)、目付の矢部彦五郎(名は定令)が老中の松平定信に、今後は旗本の妻女も御乳持を務めるべきであると上申し、旗本の妻女からも採用されるようになります。それは従来の慣例を破る大きな改革でした。
矢部が改革を唱えたのは、御乳持の人数不足を解消するだけでなく、その方が若君姫君が健やかに成長すると考えたからです。すなわち御目見以下の〝賤しい〟御家人の妻女たちは、お乳はさし上げても、抱いたり添い寝をしたりすることは憚られる。これでは赤ちゃんがかわいそう。若君姫君が安心してすくすく育つためにも、旗本の妻女が抱きながらお乳をあげ、あるいは乳首を含ませて添い寝することが必要だというのです。
旗本の森山孝盛(もりやま・たかもり)が寛政10年(1798)に著した『蜑の焼藻の記』に、この〝御乳持改革〟の経緯が書かれています。改革の手始めに御乳持に選ばれたのは、ほかでもない、目付を務めていた孝盛の娘でした。目付の娘が選ばれた背景には、彼女に大奥の内情を探偵させようとする定信の意向がはたらいていたとも記されています。
展示資料は、全1冊。