国立公文書館 統括公文書専門官室
上席公文書専門官 寺澤正直
はじめに
アーカイブズ機関に勤めていると「アクセス」と名の付く専門用語に出会うことはしばしばある。アクセスポイント、オープンアクセス、アクセシビリティ、探せば、まだまだあるに違いない。例えば、アーカイブズ機関までの道のりをアクセスと呼び、インターネット上のウェブサイトにたどり着くこともアクセスと呼ぶ。アクセスという言葉は、便利な言葉である一方で、日本語にすることが難しい。そこで、本稿では「Access」について、片仮名の「アクセス」を用いることとする。
本稿は、アメリカ・アーキビスト協会(Society of American Archivists、SAA)編による『アーカイブズ基礎シリーズⅢ:アーカイブズと手稿のレファレンスとアクセス(原題:Archival Fundamentals Series Ⅲ:Reference and Access for Archives and Manuscripts、以下「本書」という。)』[1]を取り上げ、その中でもアクセスを中心に紹介する。なお、もう1つのキーワードである「レファレンス」を中心とした本書の紹介記事があるので、参考情報としてお知らせする[2]。
本書の概説に入る前に、日本とアメリカのアーカイブズにおけるアクセスについて、簡単に触れておきたい。
アメリカでは、SAAの用語集にある「アクセス(access)」から、次の3つの定義を確認できる[3]。
1.カタログ、インデックス(index)、検索手段(finding aid)、又はその他のツールの使用を通じて
関連情報の場所を検索する能力
2.法的に定められたプライバシー、機密性及びアクセスする権限(security clearance)の制限内で、
利用(相談又はレファレンス)のために情報の場所を検索及び探索するための許可
3.ストレージメディアから情報を探索する物理的なプロセス
日本では、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)に関連する「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン」(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)の中にアクセスという語句を確認できるが、「不正アクセス」「アクセス制限」といった個人情報漏えい防止のための措置や情報セキュリティに関する用語に留まる[4]。また、国立公文書館が取りまとめた「アーキビストの職務基準書」(平成30年独立行政法人国立公文書館)の中に、アクセスという語句は1つも確認できない[5]。しかしながら、「利用審査の結果、原資料にアクセスできる」「インターネットを通じて、デジタルアーカイブから資料の目録やデジタル画像にアクセスできる」といった使い方で意味が通じるように、アクセスという語句は、「公開」「閲覧」又は「利用」の意味を広範囲で含む語句であると筆者は捉えている。
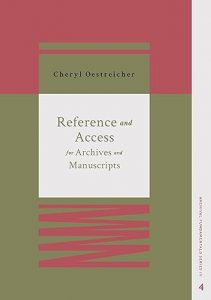 1.アーカイブズ基礎シリーズⅢ:アーカイブズと手稿のためのレファレンスとアクセス
1.アーカイブズ基礎シリーズⅢ:アーカイブズと手稿のためのレファレンスとアクセス
(1)本書の基本情報
本稿は、先に公表した筆者の記事の続きにあたるため、本書の基本情報、著者及び構成の概要については、そちらを参考にして欲しい[6]。なお、本書は、大学アーカイブズや地域のアーカイブズといった比較的小規模のアーカイブズ機関におけるレファレンスやアクセスを取り上げている印象を受ける。
(2)本書の構成
本書の構成は次のとおりである。
第2章 レファレンスの技能と知識
第3章 利用者
第4章 レファレンスのやり取り
第5章 物理的アクセス
第6章 知的アクセス
第7章 仮想アクセス
第8章 倫理、利用者のプライバシー、アクセシビリティ
第9章 法的規制
第10章 利用方針
第11章 アウトリーチ
第12章 レファレンスプログラムの評価
第13章 アクセスとレファレンスの未来
本書はレファレンスとアクセスの2つのテーマを扱っているが、本稿では、アクセスを中心に取り上げる。具体的には第5章から第8章及び第11章を概説する。なお、第9章はアメリカ合衆国における法的規制について、第10章は複写や貸出しに関する一般的な利用サービスついての記載であるため、本稿では割愛する。
2.物理的アクセス(第5章)
第5章「物理的アクセス」では「閲覧室と調査エリア」「スタッフの配置(Staffing)」「〔利用者の〕登録(Registration)」「利用と取扱い(Use and Handling)」「セキュリティ」について取り上げている。本書では、「物理的アクセス」についての明確な定義はないものの、アーカイブズ機関に直接訪れる利用者を対象として、アーカイブズ資料に対して物理的に必要な要件についてまとめている[7]。
(1)閲覧室と調査エリア(Reading Room and Research Area)
閲覧室について、SAAの用語集を元に、「利用者が書庫の所蔵資料に対して作業するために設計された安全な空間エリア」[8]と説明している。その上で、閲覧室と調査エリアの区分の特徴について触れている。具体的には、スタッフが物理的に区分けされている場合を閲覧室、スタッフが指定されたエリアに配置されているような場合を調査エリアと説明している。
(2)スタッフの配置(Staffing)
スタッフを配置することの目的として、閲覧室の監視、レファレンスのやり取りの対応、及び資料の探索に必要であると説明している[9]。日本国内の一般的な閲覧室でもよく見られる「シングルスタッフ」や「当番制(Rotating Services)」の説明がある一方で、アーカイブズ機関の多様な機能の対応を行う「キュラトリアルスタッフ(Curatorial Staff)」、レファレンスを行うアーキビストの窓口のような、特定の機能を提供する「機能的サービス(Functional Services)」、大規模な機関で設置される「マルチサービスポイント(Multi Service Points)」[10]、についても説明している。
(3)利用と資料の取扱い(Use and Handling)
アーカイブズのコレクションには様々な形式(format)の資料があり、その形式ごとに、閲覧室での提供方法は異なることを説明している。本書では、①紙媒体の記録、②「写真、ネガ、マイクロフィルム」、③「地図、建築の記録、ポスター、その他通常のサイズよりも大判の資料」④視聴覚の資料の形式別に、その取扱いや提供方法について説明している[11]。
(4)セキュリティ(Security)
物理的アクセスの中で重要なことの1つとして、資料の「セキュリティ対策」を取り上げている。具体的には、①閲覧室におけるコレクションへのアクセス、②盗難や破損を防ぐための方針、③書架の維持管理、で構成される。例えば、盗難を防ぐために閲覧室にバックやコートを持ち込ませないこと、閲覧室を監視(Monitoring)すること、書庫への入室を制限すること、を挙げている[12]。一見、アクセスとは真逆の「制約」のように見えるが、このようなセキュリティの要件があるからこそ、「安全な空間エリア」としての閲覧室の実現につながると言える。
3.知的アクセス(第6章)
第6章「知的アクセス」では「編成と記述」「アクセス出力」について取り上げている。知的アクセスとは、「〔利用者が〕発見及び利用可能となるように、ツール又はシステムを通じて使用できるようにしたアーカイブズ資源の記述又は情報」[13]のことを意味し、「物理的アクセス」と対照させて使われることの多い用語である。本書では、知的アクセスについて「コレクションの検索、利用及びアクセスに必要な全ての情報を網羅しているもの」、「この情報を共有する方法は、Webサイト、検索手段、目録、インベントリ、データベース、オンライン コレクション、リサーチガイド、インデックス等、仮想的にも印刷物でも多数ある」と説明している[14]。
(1)編成と記述(Arrangement and Description)
編成とは「資料の出所ともともとの秩序を考慮して、資料群を体系づけること。またコレクション内の資料の構成と順序を決めること」を意味する。また、記述とは「資料を表現するために作成されたデータセット(検索支援(finding aids)や目録など)。また、こうしたデータセットを作成するプロセス」を意味する[15]。
本書では、「編成と記述」について、「統制(control)のレベル」「物理的な編成」「記述」について取り上げ、SAAの用語集から「出所(provenance)」「コレクション(collection)」「シリーズ(series)」といった用語を確認しつつ、利用者が資料を探す場合の考え方の基礎となるコレクションの物理的及び知的コントロールを中心に説明している[16]。
(2)アクセス出力(Access Output)
本書では、「アクセス出力」について、「コレクション管理システム」「検索手段」「目録」「代替フォーマット」「オンライン検索」「印刷資源」について取り上げ、知的アクセスに関する具体的なツールについて説明している[17]。
4.仮想アクセス(第7章)
第7章「仮想アクセス」では、「ウェブサイト」「デジタルコレクション」「システムとフォーマット」「メタデータ」「仮想閲覧室」「デジタル調査における革新」について取り上げている。「仮想アクセス」について明確な定義はないとしながら、アーカイブズ機関がオンラインで提供する情報とデジタルコンテンツへのアクセスに関する事項がまとめられている[18]。なお、仮想アクセスが行える環境が整備されることで、利用者は来館することなく、仮想及び遠隔からのレファレンスを受けることができる[19]。このような遠隔等からのレファレンスについても、本書で取り上げている。
(1)ウェブサイト(Websites)
本書では、効果的なウェブサイトとは、利用者の発見に直接役立つ情報と資源を提供すると説明している[20] 。また、ウェブサイトの管理にあたり、コンテンツの正確性、関連性、最新性を確認して更新することが重要であると説明している[21] 。さらに、ウェブサイトの標準的な構造は存在しないとしながら、適切なレベルの情報を維持する上で中心となる次の構成を紹介している[22]。
ウェブサイトの構造 Web サイトの推奨構成
| 項目 | 具体的な内容 |
| 一般情報 | フィードバック又は提案、営業時間、要領、駐車場/訪問、ソーシャルメディア、スタッフ名簿、戦略計画 |
| コレクション情報 | コレクション構築方針/記録管理方針、コレクションの所蔵と記述、寄贈 |
| コレクションの利用 | 授業の指示コレクションの検索、カリキュラムと教材、デジタルコレクション、検索補助データベース、フォーム、閲覧室のガイドライン、主題研究ガイド |
| ポリシー/手順 | ADA準拠[23]とアクセス、著作権、デジタル写真、貸出、使用/公開の許可、プライバシー ポリシー、複製 |
| アウトリーチ | カレンダーイベント、展示会、図書館の友、ギフトショップ、参加方法/ボランティア、ニュース、ニュースレター、出版物、賞品/旅費/研究助成金、プログラミング、ツアー、バーチャルツアー |
(2)デジタルコレクション(Digital Collection)
本書では、「デジタルコンテンツ」の概念が広く、デジタル複製、ディスクに保存される電子ファイル、ソーシャルメディア、ウェブサイト、電子メール、音声・映像の電子ファイル等多岐に渡り、これらのデジタルコンテンツで構成されるデジタルコレクションへのアクセスの提供は、本書の第2版が出版された2005年以降、飛躍的に成長し、変化していると説明している[24]。なお、「デジタルコレクション」について、「デジタル化(Digitization)」された資料と、作成時点から電子的に作成された「ボーンデジタル(Born Digital)」の2つに大別して説明している[25]。
(3)システムとフォーマット(System and Formats)
本書では、デジタルコンテンツのフォーマットによってシステムが異なり、アーキビストは様々なコンテンツ管理システムを通じてデジタルコンテンツを提供する、と説明している。また、次のシステムを取り上げ、そのシステムが扱うデジタルコンテンツとシステムの概要が示されている[26]。
・ウェブサイト(Websites)
・ソーシャルメディア(Social Media)
・コンテンツ管理システム(Content Management Systems (CMS))
・デジタル資産管理システム(Digital Asset Management (DAM) Systems)
・機関リポジトリ(Institutional Repositories (IR))
(4)メタデータ(metadata)
本書では、「記述」とは別に「メタデータ」の項目が用意されている。メタデータについて「検索用にコンテンツを記述、編成、管理する構造化した情報であり、長期的なアクセスを確保するために、より広範囲な相互運用性や識別を可能とするもの」と説明している[27]。また、デジタルコンテンツが、アナログ資料をデジタル化したもの、ボーンデジタルのものにかかわらず、メタデータは重要であると説明している。少なくとも、タイトル、作成者、年月日、主題の基本的な情報が含まれていれば、ある程度のアクセスが可能となること、スタッフの配置や作業時間が許せば、その他の情報を追加することで、検索性が向上すると説明している[28]。
5.倫理、利用者のプライバシー、アクセシビリティ(第8章)
第8章「倫理、利用者のプライバシー、アクセシビリティ」では、章タイトルのとおり、「倫理」「利用者のプライバシー」「アクセシビリティ」の3つの包括的な概念について取り上げている。これらは個別の概念のように見えるが、「〔これらの概念は〕利用者を第一に考え、アーカイブズ施設と利用者との間の全てのやり取りが平等となること目的とするという点で共通する」と説明している[29]。
(1)倫理(Ethics)
本書では、アーキビストは、利用者に平等なサービスを提供し、利用者の質問や視点を尊重し、資料へのアクセスを確保するために必要なあらゆる作業を実行する必要があると説明している[30]。本書内において2012年改訂の「SAAコアバリューステートメントと倫理綱領」[31]の次の記述を用いて、アクセスと利用に関する慣行について紹介している。
・アーカイブズ資料を保管する根本的な理由は利用であることを認識し、アーキビストは、機関の使命と対象となる
利用者の状況において、管理下にある記録へのオープンで公平なアクセスを積極的に促進する。
・制限を最小限に抑え、アクセスのしやすさを最大限に高める。
・あらゆる形式のアーカイブ資料の継続的なアクセス性と理解可能性を促進する。
・アーキビストは、責任ある使用を促す戦略とともに、機関のアクセスポリシーを策定し普及させる。
・アーキビストは、寄贈者や移管元の機関と協力して、いかなる制限も適切に、十分に文書化し、制限を実施する。
・書庫が機密情報や専有情報を保護するために制限を必要とする場合、そのような制限は公平な方法で実現する
必要がある。
・アクセスに関する全ての課題について、アーキビストは、競合する原則と利益のバランスをとる実用的な解決策を
求める。
また、このような原則は、SAAだけではなく、カナダ、オーストラリア、イギリスのアーキビスト協会の倫理綱領にも含まれると説明している[32]。
(2)利用者のプライバシー(Patron Privacy)
本書では、SAA倫理綱領の、「アーキビストは、研究の機密性を維持し、機関のポリシーに従って利用者について収集した個人情報を保護することにより、全ての利用者のプライバシーの権利を尊重する」を根拠としてプライバシーの保護について説明している [33]。具体的な保護すべき利用者情報として、利用者の身元、使用するコレクションに関する情報、研究の目的及びリポジトリによって収集されたその他のデータを挙げている[34] 。
(3)アクセシビリティ(Accessibility)
アクセシビリティとは、一般的に「入手可能性(しやすさ)」や「アクセス可能性(しやすさ)」と翻訳される。本書では、「アクセシビリティ」について、「物理的アクセシビリティ」「仮想アクセシビリティ」「言語」の3点を取り上げている。「物理的アクセシビリティ」は、身体的な障害を持つ方に対応するためのアクセスビリティであると説明している。具合的には、車椅子用のスロープや通路、自動ドア、エレベーター等とある。また、建物による配慮は、物理的アクセシビリティの1つの側面であり、調整可能なテーブルや椅子の高さ、調光可能な照明もその1つと説明している[35] 。「仮想アクセシビリティ」はデジタルコンテンツのアクセシビリティであると説明している。オンライン資源は、単一の能力や感覚に依存しない方法で、誰もが利用又は表示できる場合を、アクセシビリティがあるとしている。見出しやリンクの色、理解を向上させるために画像に説明テキストを追加することも、このアクセシビリティの1つと、本書では説明している[36] 。「言語」はアクセシビリティの重要な側面であるとし、言語によるアクセスの障壁を軽減又は排除するための方法をいくつか提示している。具体的な対応方法として、複数言語を話せる人員を雇用する、オンライン翻訳等のツールを手元に用意する、筆記具を提供する等の方法が示されている[37]。
6.アウトリーチ(第11章)
第11章「アウトリーチ」では、「開発と戦略」「ソーシャルメディア」「クラウドソーシング」「友の会」について取り上げている。本書ではSAAの用語集を用いて、アウトリーチについて「リポジトリの使命に関連するニーズを持つ利用者を特定してサービスを提供し、それらのニーズを満たすようにサービスを調整するプロセス」と定義を確認した後、アウトリーチはこの定義を超えて、「アーカイブズの目的とその社会的役割について、利用者を教育すること」と説明している [38]。
(1)開発と戦略(Development and Strategy)
本書において、アウトリーチは慎重な検討を必要とする投資であると説明している。また、最初のステップは、活動の目的、目標と結果、対象者、活動の種類、特にスタッフと資源の可用性に基づいて戦略を決定することとある。本書で例示されるアウトリーチ活動は次のとおりである[39]。
アウトリーチ活動の例
| 分類 | 具体例 |
| プログラム | 講演、プレゼンテーション、パネルディスカッション、ディスカッショングループ、ブラウンバッグランチョンミーティング、シンポジウム、カンファレンス |
| 展示 | 物理的な展示、デジタル展示 |
| ツアー及び一般公開 | 閉架書庫のガイド付きツアー |
| カリキュラムと指導 | 実践的なワークショップ、研究コンテスト、カリキュラムと課題 |
| 広報 | ニュースレター、パンフレット、メディア報道、ソーシャルメディア |
(2)ソーシャルメディア(Social Media)
本書では、ソーシャルメディアは、マーケティングとアウトリーチ戦略の両方の側面があると説明している[40]。ソーシャルメディアを利用する潜在的な目的として、①直接の訪問者と遠隔地の訪問者の両方によるコレクションの利用を促進すること、②認知度とブランドを構築すること、③コレクションのコンテンツを宣伝すること、④アドボカシー活動を行うこと、⑤寄贈を促すこと、を挙げている[41]。
(3)クラウドソーシング(Crowdsourcing)
本書では、クラウドソーシングは、オンラインでウェブサイトの視聴者と関わるための最近の取組と説明している[42]。具体的には、タグ付け、文字起こし又はその他の手段を通じてコレクションの記述に貢献することとある[43]。アーカイブズ機関の利点として、①参加した利用者がアーカイブズの重要性をより強く認識するようになること、②ボランティアが知識を提供するためにアーカイブズ施設にいる必要がないこと等を挙げている。筆者が知る日本国内の②の事例としては、京都大学古地震研究会が運営する『みんなで翻刻』が同様の取組であると捉えている[44]。
おわりに
本稿では、本書の中から「アクセス」を中心に紹介した。アクセスには、物理的アクセス、知的アクセス、仮想アクセスの3つの種類があることを確認することができた。また、利用者がそれぞれのアクセスを可能とするために、整備が必要とされるルール、インフラ等の設備、コンテンツ等がまとめられている。さらに、倫理、利用者のプライバシー、アクセシビリティといった異なる包括的な視点から、アクセスを捉えていることも確認できた。もし、アーカイブズ機関における「アクセス」について、より体系的に理解を深めたい方がいるのであれば、本書を確認することをお勧めする。
[注]
[1]Cheryl Oestreicher (2020) “Archives Fundamentals Series Ⅲ:Reference and Access for Archives and Manuscripts”, Society of American Archivists。
[2]寺澤正直「アメリカ・アーキビスト協会編アーカイブズ基礎シリーズⅢ『アーカイブズと手稿のためのレファレンスとアクセス』を読む①~レファレンスを中心に~」『アーカイブズ』第93号、2024.8.30、https://www.archives.go.jp/publication/archives/no093/16093,accessed 2025-01-20.
[3]SAAウェブサイト.「reference」,https://dictionary.archivists.org/entry/reference.html,accessed 2025-01-20.
[4]当該ガイドライン第8条第1項第2号に「当該特定歴史公文書等に記録されている個人情報に対する不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為 をいう。)を防止するために必要な措置」とある。
[5]『アーキビストの職務基準書』.https://www.archives.go.jp/about/report/pdf/syokumukijunsyo.pdf,accessed 2025-01-20.
[6]前掲注2.
[7]前掲注1、p.52.
[8]前掲注1、p.52.SAAウェブサイト「reading room」,https://dictionary.archivists.org/entry/reading-room.html,accessed 2025-01-20.
[9]前掲注1、p.54.
[10]前掲注1、pp.54-56.
[11]前掲注1、pp.58-60.
[12]前掲注1、p.60.
[13]SAAウェブサイト「intellectual access」, https://dictionary.archivists.org/entry/intellectual-access.html,accessed 2025-01-20.
[14]前掲注1、p.65.
[15]渡辺悦子「アーカイブズの「編成」と「記述」あれこれ~アメリカ・アーキビスト協会編アーカイブズ基礎シリーズⅢ『アーカイブズと手稿を編成・記述する』を読む~」『アーカイブズ』第91号、2024.2.29、https://www.archives.go.jp/publication/archives/no091/14804,accessed 2025-01-20.
[16]前掲注1、pp.65-68.
[17]前掲注1、pp.69-73.
[18]前掲注1、p.74.
[19]前掲注2.本文の3(2)「仮想及び遠隔からのレファレンス(Virtual and Remote Reference)」に紹介される。
[20]前掲注1、p.75.
[21]前掲注1、p.75.
[22]前掲注1、p.75.
[23]ADAは、障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act)の略称。
[24]前掲注1、p.77.
[25]前掲注1、pp.77-79.
[26]前掲注1、pp.80-81.
[27]前掲注1、p.81.
[28]前掲注1、pp.81-82.
[29]前掲注1、p.87.
[30]前掲注1、p.87.
[31]SAAウェブサイト「Core Values & Code of Ethics」, https://www2.archivists.org/statements/saa-core-values-statement-and-code-of-ethics,accessed 2025-01-20.なお、本書内では2012年改訂とあるが、本ウェブサイトでは、2020年改訂であることの記載が確認できる。
[32]前掲注1、p.88.
[33]前掲注1、p.88.
[34]前掲注1、p.88.
[35]前掲注1、p.91.
[36]前掲注1、pp.91-92.
[37]前掲注1、p.92.
[38]前掲注1、p.127.
[39]前掲注1、p.129.本文内のFIGURE 14を元に表として、筆者が整理したもの。
[40]前掲注1、p.130.
[41]前掲注1、p.130.
[42]前掲注1、p.131.
[43]前掲注1、pp.131-132.
[44]京都大学古地震研究会「みんなで翻刻」, https://honkoku.org/,accessed 2025-01-20.
