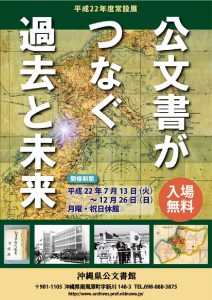沖縄県公文書館指定管理者(公財)沖縄県文化振興会
公文書管理課 福地洋子
はじめに
沖縄県公文書館(以下、「館」という)は、平成7年8月に開館しました。(公財)沖縄県文化振興会(以下、「財団」という)は、平成8年4月に沖縄県から館の運営業務を受託し、平成19年4月以降、指定管理者として30年近く運営に携わっています[1]。現在、公文書館の責務、役割機能を果たすため、財団の公文書管理課に配属されたプロパー職員(以下、「職員」という)9名が、県と連携しながら公文書館業務の中心的な役割を担っています[2]。
私は、平成16年4月に財団職員(公文書専門員)として採用されました。米国収集資料担当として採用された当時の私は、米国収集資料を専門としていくものと思っていましたが、今年で勤務20年目を迎えた現在、保存以外の部門でさまざまな業務経験をつみかさね、現在は館の管理運営を担当する総務班で勤務しています。本稿では、これまでの専門職員としての業務経験と現在の職務である総務業務との関わりについて述べたいと思います。
1 専門職員としての経験
(1)米国収集資料業務
入職して2年間は、米国収集資料の受入及び整理業務を担当しました。館では平成10年度から17年度にかけて米国国立公文書館を中心に職員が沖縄関係資料を調査、収集するプロジェクトを実施しており、私は、米国に駐在する職員から送付された英文資料の件名翻訳、目録作成等の整理業務を担当しました。米国収集資料の業務では、入職して2ヶ月後に行った沖縄戦映像フィルムの公開が印象に残っています。平成16年6月23日の慰霊の日を前に公開することとなり、マスコミ向けの資料作成、館長コメント作成など、とにかく無我夢中で準備に奔走したことを覚えています。映像公開に伴って普及部門が開催した映写会には、1日2回の上映を3回に増やすほど、多くの県民が来館し、沖縄戦への関心の高さを実感しました。同時に、沖縄戦で記録を焼失した県民にとって、映像フィルムは重要な記録であり、公文書館がその記録を後世へつなぐ重要な役割を担っていることを初めて意識した日だったと思います。
(2)県文書業務
平成18年度以降、沖縄県公文書館の運営は、沖縄県が示した「沖縄県公文書館基本運営方針」[3]をもとに、県文書を中心に所蔵資料の充実を図ることとなりました。私は、平成19年度から30年度にかけて、県文書の受入評価選別を6年、整理業務を3年経験しました。
受入業務では、県総務私学課の文書管理状況調査に同行した引渡促進活動が特に印象として残っています。また、県の総務私学課への研修として、県庁内の部署を回り、保存期間満了後の文書についての調査も行いました。部署によっては琉球政府時代の文書を保管していたので、公文書館への引渡をすすめたところ、宮古や八重山教育事務所など数カ所から引渡がありました。
沖縄県公文書館は、知事部局を中心に約3,000箱の県文書が引き渡されます。引き渡された文書を速やかに選別するため、平成18年度から導入されたシリーズによる評価選別を実施しています[4]。シリーズによる評価選別は、事務事業の規則性・継続性の多い公文書の特徴を生かした手法で事務事業ごとに根拠となる法令や業務の流れを分析し、作成または取得する文書をまとめ、保存すべき文書を判断します。評価選別では、業務分析、文書類型の洗い出しをして、判断基準となる選別シートを作成します。その結果、次年度以降の受入分については、作成された選別シートに基づき選別を進めることができます。この方法に基づき、年3,000~5,000箱を評価選別していました。また、整理業務の工程においても、選別シートの業務概要や文書類型を目録採取に生かすことができるので、年間で約2,000簿冊の県文書公開を進めて行く上でも役立ちました。
一方で、規定に基づいて必ずしもすべての文書が県から引渡されていないため、重要な文書が保存されない、という沖縄県文書管理全体の課題があります。現在、沖縄県では公文書管理条例の制定が検討されており、重要な公文書が公文書館へ適切に保存されるよう改善していくことを期待しています。
(3)閲覧・普及業務
閲覧業務は、平成22年度から平成24年度、令和元年度から2年度の計5カ年経験しました。来館、電話、メール等による利用に関する対応、閲覧窓口での利用審査、レファレンス、行政利用について職員4名(令和元年度から2年度は、職員1名(福地)と嘱託員3名)が中心となって対応していました。閲覧業務では、県文書の評価選別や整理業務の経験や知識がレファレンス業務に役立ちました。また、整理した県文書の利用状況や県文書整理数の増加にともなって利用が増えていることも実感でき、評価選別業務を担当する際に、よりやりがいをもって取り組むことができました。
普及業務においても県文書の評価選別業務の経験を生かすことができました。平成22年度に初めて常設展を担当したとき、公文書館が県民の共有財産としてどのような公文書を保存し後世につないでいくかを伝える展示として「公文書がつなぐ過去と未来」としました。その際、評価選別の判断としての3つの視点「意思決定に関する文書」「社会情勢又は県勢に関する文書」「住民の権利利益に関する文書」を各セクションのテーマにしました。来館者へ公文書についてわかりやすく伝えられたか、反省点もありましたが、企画してよかったと思います。
2度目の閲覧業務では、沖縄県の新型コロナウイルス感染症拡大にともなう長期の臨時休館を経験しました。その際、遠隔地複写やレファレンス強化など非来館型の閲覧サービスに取り組みました。また、利用者や職員の感染予防対策のため、閲覧室の予約制や滞在時間制限を導入しました。新型コロナ感染症の状況の変化に対応しながらサービスを続けるのは大変でしたが、災害時における閲覧サービスのあり方を検討する機会にもなりました。公文書館は、感染症だけでなく、台風や停電など災害時に備えて、利用者の安全確保をしながら閲覧サービスを提供する必要があります。コロナ禍での閲覧業務の経験は、館の施設管理を担当する現在の総務業務にも役立っています。
2 専門職員の経験と総務業務との関わりについて
令和3年4月に総務班長として異動になり、今年で4年目になります。総務班は、公文書管理課の総務、会計、予算、人事、労務管理などを担当する管理運営部門と施設の修繕、環境衛生、警備業務を担当する施設管理部門があり、各部門の嘱託員や管理運営主任専門員(任期付職員)を中心に館の管理運営業務を行っています。私は、班の総括業務のほか、主に館の予算、決算、人事業務を担当しています。配属当初は、私自身総務の業務経験もなく、慣れない業務に戸惑いもありましたが、班の職員の協力を得ながら館の運営がスムーズにいくように心がけています。
ところで、これらの総務業務は、一見アーキビストの業務とあまり結びつかないのではないかと思われるかもしれませんが、個人的にはさまざまな場面でアーキビストとしての業務経験や知見が生かされていると実感しています。例えば、職員採用業務においては、県や財団幹部への調整の場では、アーキビストのさまざまな職務を理解した上で説明することが必要になります。特に、説明の際は、認証アーキビスト資格制度のおかげで説明しやすくなったと実感しています。また、予算編成では、各部門からの業務計画をもとに編成しますが、業務全体を把握して俯瞰的に考える視点というのは評価選別業務と似ていると思います。館の管理運営業務の範囲は幅広いので、一人で進めるものではなく、多くの方と調整しながら進めていく能力も重要だと感じています。これからも職員をはじめさまざまな方との協力を得ながら館の運営に貢献できればと思います。
おわりに
沖縄県公文書館の業務は、受入評価選別、整理、保存修復、閲覧、利用普及、デジタルアーカイブと内容が多岐にわたっています。現在、財団職員7名(全員プロパー職員)が認証アーキビストを取得しており、それぞれの部門で経験を積み、知識を得て、異動した部門でその知識をブラッシュアップさせ、アーキビストとしての職務能力を高めていくことができると考えています。
沖縄県公文書館は、来年開館30年で大きな節目を迎えます。これまでのアーキビストとしての業務経験をもとに、今後も職員と協力しながら館の運営に携わっていきたいと思います。
[注]
[1]平成8年4月の業務受託時の財団組織名は、財団法人沖縄県文化振興会である。平成23年4月に公益財団法人へ移行した。財団は、法人運営及び文化事業を所管する文化芸術推進課と公文書事業を所管する公文書管理課の2課で組織される。財団の運営は、沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課が所管している。参考「沖縄県文化振興会について」https://okicul-pr.jp/600/2014-04-13-20-33.html
[2]館の運営は、沖縄県総務部総務私学課が所管している。
[3]「沖縄県公文書館運営基本方針」(平成18年8月25日総務部長決定)
https://www.archives.pref.okinawa.jp/wp-content/uploads/koubunsyokanunei-kihonhoushin.pdf
[4]大城博光「公文書の評価選別ガイドライン構築に向けた中間報告」(『沖縄県公文書館研究紀要第11号』、2011年)
https://www.archives.pref.okinawa.jp/wp-content/uploads/kiyou11_07.pdf